自宅
「ねえ、ちょっと散歩でも行こっか」
時間は深夜0時を回ろうとしていた。
ダイニングでスマホをいじっていた私に、妻が明るい声でそう言った。
「今から? こんな時間に?」
「最近あったかくなってきたし、ちょっと体なまっちゃって、体を動かしたい気分なんだよね」
昔から、思いついたことをすぐに実行する彼女の行動力には、どこか尊敬している部分があった。
その自由さに惹かれたのも、彼女を好きになった理由のひとつだった。
私は二つ返事で、散歩に行くことを決めた。
彼女を一人で深夜の街に出すわけにもいかなかったし、彼女に誘われて、私自身も体を動かしたくなっていた。
明日も休みだし、深夜の散歩なんて面白そうだなと――そんな軽い気持ちで、私は玄関で靴を履いた。
深夜の街
靴を履き、玄関を出た瞬間、ひんやりとした空気が肌に触れた。
昼間とはまるで違う、静まり返った住宅街が、私たちを包み込む。
風は心地よく、私たちはしばらく行き先も決めず、ただ歩き回った。
街灯がぽつぽつと道を照らしているだけで、人の気配はまるでない。
「やっぱり夜は静かだね」
妻はそう言いながら、私の少し前を歩いたり、ふいに隣に並んだりと、気ままな歩調で進んでいく。
時おり、遠くで車やバイクの排気音が聞こえるだけで、街はひっそりと眠っているようだった。
家々の窓にはカーテンが閉じられ、灯りはほとんど見えない。
人々が暮らしているはずなのに、まるで誰もいないかのような静けさに、少し不思議な気分になった。
やがて、少し広めの道路を渡り、中学校の脇を通って川沿いの道に出る。
橋を渡ったところで引き返すことも考えたが、ふと、もう少し先に大きな公園があることを思い出した。
「せっかくだし、行ってみようか」
妻と相談して、私たちはその公園を目指すことにした。
深夜の公園
しばらく歩いて、私たちは公園に着いた。
この公園には、小動物を飼育しているミニ動物園と、ふれあいスペースのような一角がある。
休日ともなれば、子どもや家族連れでかなり賑わう場所だ。
ゆっくり全体を歩いて一周すれば、30分はかかるだろう。
そんな賑やかな昼間の印象とは裏腹に、深夜の公園はまるで別の場所だった。
街灯はところどころにしかなく、広い敷地の大半が暗闇に沈んでいる。
もちろん、人の姿はどこにもない。
入り口からは、公園奥にあるミニ動物園の管理棟がぼんやりと見えた。
確か、トイレや自動販売機、ちょっとした売店などもそのあたりにあったはずだが、
今はすべて暗闇に包まれ、どこか息をひそめているようにも見えた。
私たちはそちらへは向かわず、右手の広場や遊具のあるほうへ進んだ。
遊具のあたりに着き、私たちはふざけて子ども用の遊具に乗ってみたりした。
けれど、辺りの静けさのせいか、キイキイと鳴る音がやけに耳に残った。
その音が、楽しさよりもむしろ寂しさを際立たせているように感じた。
なんとなく、空気がひんやりとしてきた気がする。
風は吹いていないのに、肌寒さを覚えた。
「……帰ろっか」
私がそう言ったとき、視界の端に、妙なものが飛び込んできた。
発見
「……なんだろ、あれ」
遊具のある場所からも、管理棟の端が見えていた。
その奥にあるトイレの建物が、ぼんやりと灯りに浮かんでいる。
そして、その灯りに照らされるようにして、小道に何かが置かれていた。
「ベビーカー……?」
誰もいない深夜の公園には、あまりにも場違いに思えて、私は思わず呟いていた。
小道の周りには、ちょっとした茂みなどもあり、
誰かがそこに使い古したベビーカーを放置していった可能性も、ゼロではない。
けれど、ぽつんと暗がりに佇むそれは、明らかに“道の真ん中”に置かれていて、
遠目からでも奇妙な存在感を放っていた。
静まり返った空間に、トイレの光がそれを浮かび上がらせている。
私たちは、一瞬顔を見合わせた。
言葉は交わさなかったが、「確認してみよう」という気持ちを、なんとなくお互いに感じ取っていたと思う。
あれが本当にベビーカーなのか、確信があったわけではない。
ただ、それが“夜の公園にぽつんと置かれている”という、その異様な光景に、
どこか吸い寄せられるようでもあった。
接近
ゆっくりと歩を進めるうちに、空気が少しずつ冷たく、重くなっていくような気がした。
距離にして、あと五メートルほど。
管理棟の角に差しかかったところで、妻がふと足を止めた。
顔を向けると、妻は無言のまま、じっとベビーカーを見つめていた。
その視線には、気味の悪さと、確認すべきかどうかで葛藤しているような緊張がにじんでいた。
私も、彼女に合わせて一瞬だけ足を止めたが、すぐにまた歩き出した。
妻は、何かを言おうとしたようだったが、言葉にはしなかった。
「気をつけて」とでも言いたかったのかもしれない。
けれど本当は、彼女自身も確認すべきだと思いながら、怖くて動けなかったのだと思う。
私だけに行かせてしまうことへの引け目も、少しはあったのかもしれない。
私は、なんとなく、彼女のそんな気持ちを察していた。
だからこそ、自分が、率先して確認しようと思った。
……怖くなかったわけではない。
それでも私は、ベビーカーに向かって歩きながら、あえて、明るい調子で妻に声をかけた。
「なんでこんな時間に置いてあるんだろうね。誰かが明るいうちに、忘れていったのかな」
声に出してみると、自分の言葉が、思っていた以上に、軽く響いていることに気づいた。
私は、ベビーカーのそばまで来て、少しだけ呼吸を整えた。
注視しながら近づいたそれは、思っていたよりも、普通のベビーカーだった。
ちょうどこちらに持ち手側が向いているため、中は確認できないが、
汚れているわけでも、壊れているわけでもなさそうだった。
見た目は、ごく一般的な”それ”と、変わらなかった。
けれど、こんな場所に、こんな時間に、なぜ――
自然と頭の中には、いくつかの想像が浮かんでいた。
もしかしたら、赤ちゃんが乗っているのではないか。
だとしたら、保護者はどこへ? 虐待……?
あるいは、人形をのせてベビーカーで歩き回る人がいる、という話も聞いたことがある。
どう見ても普通のベビーカーにしか見えないが、犬や小動物を乗せるペット用のカートとして使用しているのかもしれない。
もしかすると、浮浪者が荷物を運ぶために使っているということも……
考えていても仕方がないと、自分に言い聞かせるように、
私はそのままの流れで、そっと中を覗き込んだ。
帰宅
――何もなかった。
空っぽのシート。何も置かれていない。
シートの奥には、くっきりと座面の模様が見えるほどだった。
変に汚れていることもなく、破損もない。
誰かが使っていたベビーカーを、ただそのまま置いていった――
そう言えるほど、ごくごく普通だった。
だけど、なぜこんなところに? なぜこの時間に?
理由はわからないままだったが、私は少しホッとした。
ベビーカーには何も乗っていなかったことを、妻にも伝えた。
彼女は小さく頷き、少しだけ肩の力が抜けたように見えた。
このまま、ベビーカーを放置していいものかと、一瞬考えたが、なんとなく触る気にもなれず、そのまま放置しその場を後にした。
公園の入り口に戻り、特に何を話すでもなく、私たちはそのまま来た道を引き返した。
夜風は少し冷たかったが、歩いているうちに、身体も落ち着きを取り戻してきた。
ぽつりぽつりと交わす、当たり障りのない会話の中で、さっきまでの緊張も、少しずつ遠のいていった。
ただ、ベビーカーについては、これ以上、何かを詮索する気にはならなかった。
なんとなく―― 私たちは、あまり振り返らずに帰った。
もしかしたら・・
深夜の散歩から数ヶ月がたち、季節は夏の盛りとなっていた。
妻の運動への関心は、気温の上昇とともに完全に消え去ったようで、最近はもっぱら、涼しい部屋で猫とゴロゴロしているばかりだった。
あの晩の、ほんの思いつきで出かけた深夜の散歩のことなど、私も妻も、もうほとんど忘れていたと思う。
その夜も私は、寝る前にリビングでなんとなくスマホを眺めていた。
ふと、妙に引っかかるニュースが目に入った。
「道端に放置されたベビーカー 決して近寄らないで」
「道端」「放置」「ベビーカー」――
並ぶ単語を見た瞬間、忘れかけていたあの深夜の出来事が、鮮やかに脳裏に蘇った。
記事はアメリカで報じられたもので、
“田舎道に放置されたベビーカーを見つけても、絶対に近づかないこと。すぐに警察に連絡すべきだ”
――といった内容だった。
それは、車や家から人を誘い出すための罠だと説明されていた。
不用意に近づいた瞬間、物陰から襲いかかり、強盗や誘拐などの目的を果たそうとするという。
そして記事は、こう締めくくられていた。
「人々を誘い出すのに、赤ちゃんグッズは最適だ。
誰もが“助けなければ”と思ってしまう。
それが罠だと気づく前に、簡単に外へ誘い出すことができる。
人の善意を利用し、それを食い物にしようとする悪魔が、この世には存在するのだと、心に留めておくべきだ。」
その一文を読んだ瞬間、背中にひやりとしたものが走った。
――あのときのベビーカー。
あれも、誰かが近くで、私たちの様子をうかがっていたのだろうか。
小道の周りには、ちょっとした茂みがあったのを思い出した。暗がりではっきりとは見えなかったが、人が隠れていたら気付くようにも思える。ただ、トイレの裏や中に潜んでいたとしたら……
息をひそめ、こちらに気づかれないように、じっと獲物を待ち構えていたのだろうか。
私はハッとした。
あのとき、ベビーカーのすぐそばで、私は妻に声をかけていた。
自分の恐怖を隠すように、あえて明るく、はっきりと。
もしかすると、私たちが“ふたりでいる”と伝わったから、手を出さなかったのではないか。
もし、あのとき――私が一人だったら。
妻が、一人で近づいていたら……?
ガチャリとドアが開き、その音に驚いて、大げさに振り返ると、
妻が妙な顔でこちらを見ていた。
「……もう寝るよ」
彼女に言われ、私はリビングの照明を落とし、寝室に向かった。
あの出来事が何だったのか――本当のところは、わからないままだ。
公園で何か事件があったという話も聞かないし、
あのトイレの中に、誰かが潜んでいたのかどうかも、結局は確かめようがない。
けれど、あのとき感じた、言葉にできない違和感だけは、今も心のどこかに残っている。
私はこのことを、妻には話さないと決めた。
スマホをそっとオフにし、画面が真っ暗になる。
窓の外では、いつの間にか秋の虫たちが、静かな声で鳴き始めていた。
あとがき
この物語は、実際に存在するニュース記事を参考にして創作したフィクションです。
実際の事件や関係者とは一切関係ありません。
ただ、内容はほとんど実話で、実際の場面に遭遇した時は、本当に不気味で悪寒を感じました。
ニュースを後日見つけた、というのも事実で、嫌なニュースだなと思ったことを覚えています。
皆さんも、深夜に散歩をする際には、十分に気をつけてください。
※本記事の内容、文章、画像の無断転載・無断使用はご遠慮ください。


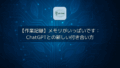

コメント